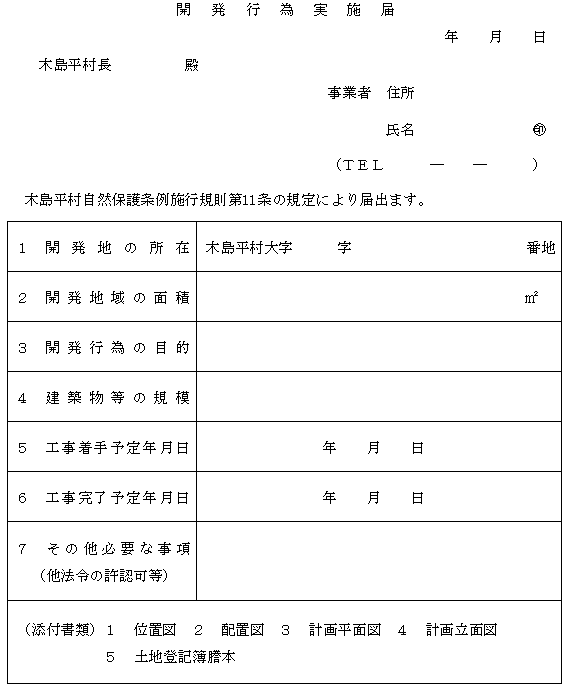○木島平村自然保護条例施行規則
平成2年3月16日規則第1号
木島平村自然保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、木島平村自然保護条例(平成2年木島平村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
(1) 自ら居住の用に供するもの
(2) 住宅の付属施設
(3) 農林漁業(第一次産業の用に供するものに限る。)の用に供するもの
(事前協議)
2 前項の規定による協議書には、次の各号に掲げる図書類を添付しなければならない。
(1) 開発行為の目的を記載した書面
(2) 開発行為の位置を明らかにした位置図
(3) 土地、建築物及び工作物の開発計画図
(4) 開発行為の土地、建築物及び工作物の面積を表示した図面
(5) 用水及び揚水の利用計画書
(6) 雨水及び排水の処理計画書
(7) し尿及びゴミの処理計画書
(8) その他村長が必要と認める図書類
(開発行為許可申請書)
2 前項の申請には、前条第2項に規定する図書類を添付しなければならない。
3 条例第16条の規定による承認を受けた者は、前項において規定する図書類のうち、村長の認めるものに限り省略することができる。
(許可の基準)
第6条 条例第18条第1項に規定する許可に際し、次の各号に掲げる開発行為は、審議会の意見を聞かなければならない。
(1) 3,000平方メートル以上の土地の形質変更
(2) 100メートル以上の道路等長狭物の設置
(3) 高さ9メートルを超える建築物の建築又は工作物の設置
(4) 面積5,000平方メートル以上の立木の伐採
(5) 太陽光等自然エネルギー発電設備の設置
第7条 条例第18条第1項第3号に規定する許可の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自然休養地の共通事項
ア 現存する植生、地形等は極力残存させること。
イ 排水路は上流の雨量又は放流先の排水能力等を充分考慮した規模及び構造とすること。
ウ 土地の形質変更は最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けること。やむを得ず移動する場合には、擁壁又は水抜きの設置若しくは段切り等を行い、土石の流出防止に万全を期することとし、擁壁の必要のない法面等については、植林及び芝張り並びに植栽等による緑化修景を速やかに実施すること。
エ 街路(開発によるもの。以下同じ。)を設置する場合は、幅員5メートル以上とし、雨水を有効に排出するために必要な措置をすること。
オ 縦断勾配が8%を超える街路は、極力建設しないものとし、やむを得ず建設する場合には、コンクリート舗装し、かつ、滑り止めの措置を講ずること。
カ 平均傾斜40度以上の土地の開発行為はしないこと。
キ 著しく傾斜(平均傾斜15度以上)している土地及びその周辺には、建築物を設置しないこと。
ク ゴミは、事業者において処理すること。
ケ 揚水設備から地下水を採取することにより水道事業の給水保全及び既設井戸からの地下水の採取に著しい支障を及ぼさないこと。
コ し尿及び雑排水は合併処理により処理水のBODを20PPM以下に処理し、地下水、河川に影響を及ぼさないよう処理すること。
サ 建築物については、次のとおりとする。
(ア) 建ぺい率は、20パーセント以下とする。ただし、条例別表第1の1の地域(以下本条において「高社山麓地域」という。)において、宿泊(分譲住宅等を含む。)、商業用店舗、休憩及び体育施設等を建築する場合は30パーセント以下、条例別表第1の3の地域(以下本条において「馬曲地域」という。)において、宿泊(分譲住宅等を含む。)、商業用店舗、休憩及び体育施設等を建築する場合は40パーセント以下とすること。
(イ) 建築物の壁面線と公道(国、県、村が管理するもの。以下同じ。)又は街路肩までの距離は、10メートル(高社山麓地域及び馬曲地域においては、5メートル)以上とすること。ただし、高社山麓地域においては、自ら居住の用に供する建築物を建築又は増築する場合は2.5メートル以上とし、屋根雪を自己の敷地内で処理できるよう臨地境界からの距離を確保すること。
(ウ) 外壁及び屋根の色彩は、原色を避け、周囲の自然と調和するものとすること。
(エ) 建築物には、公道又は街路からの進入路(宅地内通路。以下同じ。)を設置すること。
シ 開発規模に応じて、事故防止及び防犯のための街灯が設けられていること。
ス 広告物については、次のとおりとする。
(ア) 建築物の屋上には、看板類を設置しないこと。
(イ) 建築物の壁面は、直接塗料で書いた広告は行わないこと。
(ウ) ネオンサイン、蛍光塗料等の強い印象を与えるものは使用しないこと。
セ その他周囲の自然と調和する修景及び植栽を積極的に行うこと。
(2) 自然休養地のゴルフ場(練習場を除く。)
ア 開発地周辺は、20メートル以上の樹林を確保すること。
イ クラブハウス等建築物は、次のとおりとする。
(ア) 建築物の高さは、15メートル(馬曲地域においては、13メートル)以下とすること。
(イ) 建築物の壁面線から公道までの距離は、20メートル以上とすること。
(3) 自然休養地のスキー場
ア ゲレンデ及びスキーコース等の造成に当たっては、樹木の伐採は最小限にとどめ、特に景観上主要な地区は、林間コース等によること。
イ 索道及び鉄柱等の建設に当たっては、風致の維持に配慮することとし、色彩は原色を避け、周囲との調和を図ること。
ウ 建築物の高さは18メートル(高社山麓地域においては、20メートル、馬曲地域においては、13メートル)以下とすること。
(4) 自然休養地の遊園地
ア 遊園地の周辺部は、修景及び植栽等を行うこととし、境界に工作物を近接しないこと。
イ 拡声器等の設置については、周囲の環境に悪影響を与えないよう配慮すること。
(5) 自然休養地の別荘地(集合別荘を含む。)
ア 公道から20メートル(高社山麓地域及び馬曲地域においては、10メートル)及び街路から10メートル(高社山麓地域及び馬曲地域においては、5メートル)は保存緑地として確保すること。
イ 街路の建設において擁壁工事を必要とする場合は、できる限り自然石によること。
ウ 建築物については、次のとおりとする。
(ア) 建築物の高さは、15メートル(馬曲地域においては、13メートル)以下とすること。
(イ) 建築物の容積率は、40パーセント以下とすること。
(ウ) 個人の施設にあっては、2階建以下とすること。
(エ) 塀その他の遮へい物は、設けないこととし、やむを得ず設ける場合は生け垣とすること。
(6) 宅地等開発地
ア 開発地が防災、防火及び交通安全上支障がないこと。
イ 開発地区内における排水施設は、雨水及び廃水を有効に排水するとともに、周辺及び下流地域に被害が生じないような構造又は能力で配備されていること。
ウ 街路を設置する場合は、当該開発地区外の公道の機能を阻害することなく、街路の機能が有効に発揮されるよう設計されているほか、次に定めるところによる。
(ア) 幅員は5メートル以上とすること。
(イ) 雨水を有効に排水するため、必要な側溝その他適当な施設が設けられていること。
(ウ) 交通安全のための施設が設けられていること。
エ 建築物には、公道又は街路からの進入路を設置すること。
オ その他開発地区内においては、修景及び植栽等を積極的に行うこと。
(7) 自然休養地及び宅地開発地の太陽光等自然エネルギー発電設備
ア 第7条第1号又は前号の基準を遵守すること。
イ 該当自治会及び近隣関係者に対し、事業者、事業区域、事業内容及び工事の施工等について説明会を開催し理解を得ること。
ウ 該当自治会及び近隣関係者に対し、事業者、事業区域、事業内容等の変更について説明会を開催すること。
(届出書)
(身分証明書)
(適用除外の届出)
2 前項の届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地の登記簿謄本(土地を取得した場合)
(2) 貸借契約書(写)(借地の場合)
(3) 開発行為の着手を証する書面
(4) 位置図
(5) 配置図
(6) 計画平面図
(7) 計画立面図
(適用除外の特例)
第11条 この規則施行の際、既に土地の所有権登記を有するものの開発行為及び既設分譲地又は条例附則第2項に規定する分譲地を取得したもの(3,000平方メートル以上を取得し、同一目的の開発行為を行うため、この条例施行の日後に所有権移転登記をしたものを除く。)の開発行為には、第7条第1号キ及びコの(ア)(イ)(エ)、同条第3号ウ、同条第5号ア及びウの(ア)(イ)(ウ)、同条第6号ウの(ア)及びエの規定は適用しない。ただし、この規則の施行日から起算して2年を経過した日において現に工事に着手しなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定により適用を除外される場合においても、工事に着手する日の30日前までに様式第8号により、村長に届出なければならない。
附 則
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号
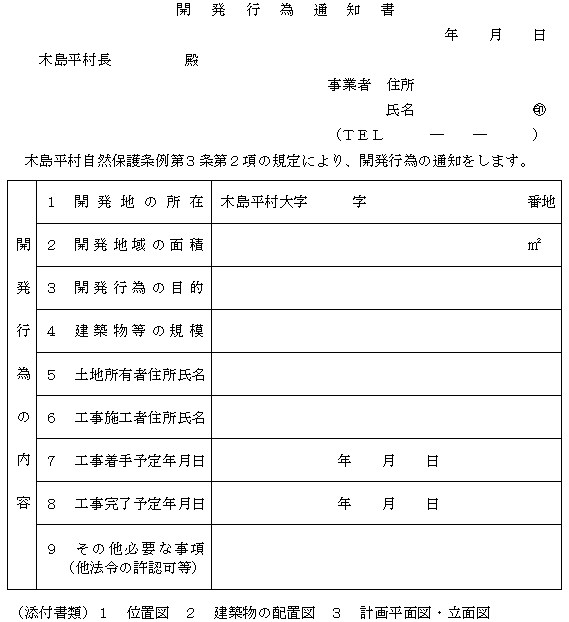
様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号
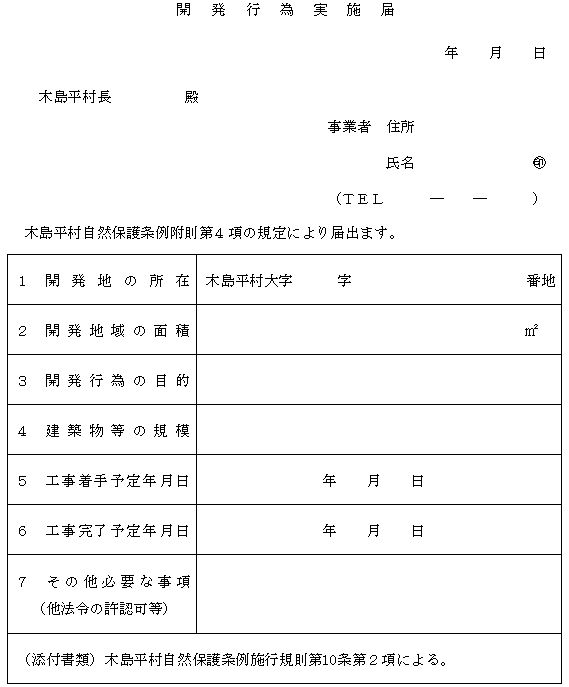
様式第8号