○扶養手当の支給に関する取扱要領
昭和61年12月1日訓令第11号
扶養手当の支給に関する取扱要領
第1 扶養親族の要件
1 次のいずれかに該当する者であること。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「未届けの配偶者」という。)を含む。以下同じ。)
(2) 満18歳未満の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満18歳未満の弟妹
(5) 重度心身障害者
(注)A 「子」、「孫」、「父母」及び「祖父母」には、養子縁組による法定血族を含む。ただし、養子の血族は、その血族関係が養子縁組後に発生した者だけが養親及び養親の血族と法定血族となる。また、養子縁組後に養親あるいは養子の配偶者となった者は、養子あるいは養親に対して法定血族ではない。
B 「子」には、認知した子、養子にいった実子は含むが、配偶者の連れ子は養子縁組しない限り含まない。
C 「父母」には、実父母は職員が養子に出た場合あるいは嫁いでいる場合であっても含むが、配偶者の父母は職員が婚家の姓を称していても養子縁組しない限り含まない。
D 「弟妹」には、父又は母のいずれかを異にする弟妹は含むが、配偶者の弟妹は職員が配偶者の父母と養子縁組しない限り含まない。
E 「重度心身障害者」とは、疾ぺい又は負傷により、その回復が永久的又は半永久的にほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができない程度と認められる者をいう。ただし、老衰を原因とする疾ぺいによるものは含まない。
なお、「重度心身障害者」は、必ずしも親族関係にあることを要しなく、年齢による制限もない。
2 次に掲げる所得等の合計額が、年額90万円未満の者であること。
(1) 給与、賃金、報酬、年金、恩給その他これらの性質を有する所得
(2) 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業から生ずる所得
(3) 公債、社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配に係る所得
(4) 法人から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息及び証券投資信託の収益の分配に係る所得
(5) 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶等の貸付による所得
(6) 雇用保険の給付
(7) 同一生計内の親族名義の所得(不労所得を除く。)の生ずる労務に従事している場合は、現実に賃金等が支払われていなくてもその労務の対価として評価される額
(注)A 「所得等」には、遺族年金、扶助料、傷病年金、傷病手当、非課税利子所得等(一時的なものを除く。)を含むが、退職一時金、退職手当、資産の譲渡所得、山林の伐採所得等(営利を目的として継続的に行なわれるものを除く。)一時的に生じた所得を含まない。
B 「所得等の合計額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)上の所得金額の計算に関係なく総収入金額(事業所得、資産所得等で所得をうるために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得をうるために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額。)をいう。
なお、当分の間給与所得以外の所得については、法第22条の規定に基づいて算定した額によるものとする。
C 「年額」とは、暦年又は年度ではなく、いわゆる1年間の総所得額をいう。
D 給与、賃金その他月を単位として恒常的に収入のある所得については、年額によらず月額(75,000円未満)によるものとする。この場合において、各月の収入額が不安定であるときは、3か月の平均月額又は年額によるものとする。
なお、季節的に雇用される者等の場合は、年額によるものとする。
E 「その他これらの性質を有する所得」には、保険等の外交員の所得を含むものとする。
F 雇用保険の給付の見込額の算定は、「(基本手当の日額)×(所定給付日数)」によるものとする。
G 「労務の対価として評価される額」とは、当該事業等による所得額を従事者数(職員を除く。専従の度合が異なるときは専従の度合)であん分して得られる額をいう。
3 主として職員の扶養を受けている者であること。ただし、次に掲げる者は、主として職員が扶養しているとは認められないものであること。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 職員を含む2人以上の扶養者によって生計を維持している者で、家計の実態、それらの扶養者の資力及び収入、社会常識等を勘案して、主として、職員の扶養を受けていると認められない者
(注)恩給又は年金に扶養家族(遺族)数に応じた加給が行われても、この加給は「扶養手当に相当する手当」に該当しない。
第2 扶養親族の届出
1 届出
職員は、次のいずれかに該当する場合には直ちにその旨(職員に(1)に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を届け出なければならないものであること。(
給与条例第15条第1項参照)
(1) 新たに職員となった者に扶養親族たる要件を具備する者がある場合又は職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(以下「増員の場合」という。)
(2) 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(以下「減員の場合」という。)
(3) 第1の1の(2)から(5)までの扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合((2)に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合((1)に該当する場合(職員に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合に限る。)を除く。)
(注)「扶養親族としての要件を具備する」とは、第1に定める要件のすべてを具備する場合をいい、「扶養親族としての要件を欠く」とは、第1に定める要件のいずれか一を欠く場合をいう。
2 届出書及び証拠書類
(1) 届出書 扶養親族届(様式第1)
(2) 証拠書類
扶養親族届には、届け出る親族(以下「届出親族」という。)又は届出の事由によって、次に掲げる証拠書類を添付すること。
ア 1の(1)の届出の場合 | 次表1に定める証拠書類(配偶者以外が届出親族の場合には、このほか次表Ⅲに定める証拠書類) |
イ 1の(2)の届出の場合 | 次表Ⅱに定める証拠書類 |
ウ 1の(3)及び(4)の届出の場合 | 次表Ⅲに定める証拠書類 |
扶養親族届に添付する証拠書類
Ⅰ 増員の場合
届出親族 | 証拠書類 |
親族関係 | 所得関係 | その他 |
配偶者 | 親族関係の証明書(婚姻の届出日が確認できるもの)ただし、未届けの配偶者にあっては婚姻関係証明書(様式第2) | 1 世帯員構成及び所得証明書(様式第3) | ※扶養状況申立書(様式第5) |
※2 所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書 | |
| ※3 雇用保険の受給に関する証明書(様式第4) | |
満18歳未満の子 | 親族関係の証明書(養子の場合は、養子縁組の事実が確認できるもの)又は医師若しくは助産婦の出産証明書 | 世帯員構成及び所得証明書(出生時の届出で配偶者が認定されている場合を除く。) | ※1 扶養状況申立書 |
※2 扶養手当等の受給の有無に関する証明書 |
満18歳未満の孫及び弟妹 | 親族関係の証明書(職員との親族関係及び生年月日が確認できるもの) | 世帯員構成及び所得証明書 | ※1 扶養状況申立書 |
※2 扶養手当等の受給の有無に関する証明書 |
満60歳以上の父母及び祖父母 | 同上 | 配偶者に同じ | ※1 扶養状況申立書 |
| | ※2 扶養手当等の受給の有無に関する証明書 |
重度心身障害者 | 親族関係の証明書(職員との親族関係が確認できるもの)ただし、親族以外の者にあっては職員との関係についての申立書 | 1 世帯員構成及び所得証明書 | 1 重度心身障害診断書 |
※2 所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書 | (症状及び終身労務に服することができるかどうかを明らかにした医師の診断書) |
| | ※2 扶養状況申立書 |
| | ※3 扶養手当等の受給の有無に関する証明書 |
Ⅱ 減員の場合
届出親族 | 証拠書類 |
親族関係 | 所得関係 | その他 |
満18才に達した子、孫及び弟妹 | | | |
死亡した者 | | | その事実が確認できる証明書等 |
離婚(縁)した者 | 親族関係の証明書(離婚(縁)年月日が確認できるもの)ただし、未届けの配偶者にあってはその事実を証明できる者の証明書 | | |
就職した者 | | 採用証明書(採用年月日及び給与月額が確認できるもの) | |
営業を開始した者 | | 営業の届けの写又はその事実が確認できる証明書等 | |
所得が生じた者又は増加した者 | | その事実が確認できる証明書等 | |
労務に服することができる程度に回復した重度心身障害者 | | | その事実が確認できる証明書等 |
他の親族等の扶養を受けることとなった者(民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けることとなった者を含む。) | | | 同上 |
行方不明者等 | | | 同上 |
Ⅲ 配偶者の有無に関する場合
証拠書類 |
親族関係の証明書、婚姻関係証明書等の親族関係及び事実発生年月日を確認できるもの |
(注)A 「親族関係の証明書」とは、戸籍の謄本又は抄本、住民票の謄本又は抄本、戸籍記載事項証明書、届出の受理証明書等をいう。
B ※印の証拠書類は、次のそれぞれの事項に該当する場合に限り添付すること。
(A) 所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書は、届出する際においてすでに世帯員構成及び所得証明書に証明されている届出親族の所得の生ずる事由又は基礎が消滅又は減少している場合
なお、「所得源の消滅又は減少の事実に関する証明書」とは、退職した者にあっては退職証明書(給与の支給を受けなくなった日が確認できるもの)、資産の売却、廃業、事業の縮少等をした者にあっては契約書の写又は市町村長等の証明書をいう。
(B) 雇用保険の受給に関する証明書は、勤労所得を有する者が退職に伴って届出する場合。ただし、国、三公社五現業、県及び市町村の常勤職員並びに公立学校の教職員であった者は、添付を要しない。
なお、雇用保険を受給中の者にあっては雇用保険受給資格者証の写をもって、また、雇用保険の被保険者でなかった者にあっては退職時の雇用主のその事実に関する証明書をもって、この証明書に代えることができる。
(C) 扶養状況申立書は、次のいずれかに該当する場合
a 届出親族が妻、子又は父母(父若しくは母に年額180万円以上の所得があるとき又は職員が長男以外の者であるときを除く。)以外の者である場合
b 届出親族が次表の「届出親族」欄に掲げる者で、かつ、届出親族と生計を一にする当該「共同扶養者の範囲」欄に掲げる親族(職員を除く。)に年額180万円以上の所得を有する者(以下「共同扶養者」という。)がいる場合
届出親族 | 共同扶養者の範囲 |
満18歳未満の子 | 届出親族の父母 |
満18歳未満の孫 | 届出親族の祖父母、父母及び兄姉 |
満18歳未満の弟妹 | 届出親族の父母及び兄姉 |
満60歳以上の父母 | 届出親族の父母、配偶者及び子 |
満60歳以上の祖父母 | 届出親族の配偶者、子及び孫 |
c 届出親族が別居している場合(配偶者を有する職員が単身赴任している場合を除く。)
(D) 扶養手当等の受給の有無に関する証明書は、届出親族と生計を一にする親族に勤労所得を有する者がいる場合
C 「その事実が確認できる証明書等」とは、扶養親族たる要件を欠くに至った事由及び年月日が確認できる市町村長、医師、雇用主等の証明書又は職員の申立書(証明が得られない場合に限る。)をいう。
第3 扶養親族の認定
1 認定権者
扶養親族の認定は、総務課長が行うものであること。(事務処理規則第6条第2項)
2 扶養親族届の受理
総務課長は、職員から扶養親族届の提出があったときは、必要事項が記載されていることを確認して扶養親族届に受理年月日を記入し、さらに次の事項を確認すること。
(1) 第2の2に定める証拠書類の添付
(2) 記載されている事項と証拠書類との符合
(3) すでに認定されている者について扶養親族台帳との符合
3 認定
(1) 増員の場合
総務課長は、扶養親族届、証拠書類等に基づいて第1に定める扶養親族としての要件のすべてをいかなる事由によりいつから具備するに至ったかを審査し、要件を具備していることを確認したときは扶養親族届の「認定決定印」欄に「

」と朱書し、第4により月額及び支給の開始年月を決定すること。(給与条例第13条第2項及び給与規則第3条第2項参照)
ただし、職員と別居している届出親族(配偶者を有する職員が単身赴任している場合を除く。)又は次のいずれかに該当する届出親族を認定するときは、任命権者と協議すること。
ア 祖父母、孫及び重度心身障害者
イ 父母及び弟妹(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(ア) 届出親族と生計を一にする親族(血族及び法定血族に限る。)に年額180万円以上の所得を有する者がいる場合
(イ) 職員に給与以外の所得が年額180万円以上ある場合
ウ 子(総務課長が次の基準(子の認定基準)によりがたいと認めた場合に限る。)
〔子の認定基準〕
子を認定する際において配偶者に年額180万円以上の所得がある場合は、原則として次の基準により職員が主として扶養していることを確認すること。ただし、配偶者が本村の給与に関する諸条例の適用を受ける者で生計を一にしているときは、上記にかかわらず、届出した職員の扶養親族として認定できるものであること。
職員の所得をA、配偶者の所得をB、職員と配偶者が扶養している子の数(満18才以上の子を含む。)をXとし、
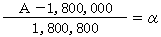
(小数点以下は、α<1のときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)、
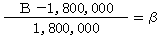
とする。
○X≦α+βの場合は、αの範囲内で認定できる。
○X>α+βの場合は、Xをαとβの比にあん分して得られるαに対する数(小数点以下四捨五入)の範囲内で認定できる。ただし、α=β=0のときは、Xの範囲内で認定できる。
(2) 減員の場合
総務課長は、扶養親族届、証拠書類等に基づいて第1に定める扶養親族たる要件のいずれかをいかなる事由よりいつから欠くに至ったかを審査し、要件を欠いていることを確認したときは扶養親族届の「認定決定印」欄に「×」と朱書し、第4により支給の停止年月を決定すること。
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者のない職員又は配偶者を有する職員となった場合
総務課長は、扶養親族届及び証拠書類に基づいて配偶者のない職員となった日又は配偶者を有する職員となった日を確認して、手当の支給額の改定年月を決定すること。
(4) 認定できない場合
総務課長は、職員から届出のあった届出親族が扶養親族たる要件を具備していない場合又は扶養親族たる要件を欠いていない場合には、扶養親族届に理由を明記し、その旨を当該職員に通知すること。(扶養親族届は、総務課長が保管すること。)
4 認定後の確認
総務課長は、職員の扶養親族が認定後も扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するほか、毎年6月1日から6月30日までの間に扶養親族現況届(様式第7)の提出を求め確認すること。
5 誤認定の取扱い
総務課長は、扶養親族たる要件を具備していない者を認定した場合には、当該認定を取り消し、その旨を職員に通知すること。
第4 扶養手当の支給
1 手当の月額
ア 配偶者 月額14,000円
イ 扶養親族たる子、父母等のうち2人 月額4,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,500円)
ウ アおよびイ以外の扶養親族 月額1,000円
(2) 職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、次の各号に該当するときは、当該職員の扶養手当の月額は、(1)にかかわらず、(1)による額から、それぞれに掲げる額を減じた額とする。
ア 当該児童手当の額が児童手当法第6条第1項第1号又は第2号の規定により算定される場合において、当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が2人以上あるとき 1,000円に当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から1を減じた数を乗じて得た額から、500円を控除して得た額
イ 当該児童手当の額が児童手当法第6条第1項第3号の規定により算定される場合において、当該児童手当に係る支給要件児童のうちに当該職員の扶養親族たる者が3人以上あるとき 1,000円に同号の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童手当に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数を超えるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数)を乗じて得た額
(注)夫婦がともに本村の給与に関する諸条例の適用を受ける者で双方に扶養親族たる子、父母等がある場合は、それらの子、父母等のうち2人を4,500円とする。また、児童手当法第4条第2項の規定により当該夫婦のいずれかが児童手当の支給を受ける場合において、当該夫婦双方の扶養親族たる満18才未満の子を合算した人数が(以下「合算した人数」という。)が2人以上あるときは、当該夫婦の扶養手当は、2人の扶養手当を合算した額を児童手当の支給を受けている職員の(1)扶養手当の月額とみなし、同額から、合算した人数を支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数とみなして(2)を適用して得られる額を減じた額とする。この場合において、扶養手当が減ぜられて支給されるのは、児童手当の支給を受けている職員(夫婦いずれか一方)であること。
2 支給の開始又は停止等
(1) 支給の開始又は支給額の増額
扶養手当の支給の開始又は支給額の増額は、次に掲げる月から月額により行うものであること。ただし、扶養親族届が事実の生じた日から15日(その期間の末日が勤務を要しない日又は休日又は指定週休日に当たるときは、それらの日の翌日)を経過した後に提出された場合は、それらの届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を増額するものであること。(
給与条例第15条第2項及び
第3項参照)
ア 新たに職員となった者に扶養親族がある場合は、その者が職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
イ 職員に扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において「事実の生じた日」とは、次のそれぞれに掲げる日をいうものであること。ただし、それらの日後に職員が主として扶養することとなったときは、主として扶養することとなった日をいうものであること。
(ア) 配偶者 婚姻の届出がされた日又は婚姻関係証明書により婚姻関係が証明された日
(イ) 子、孫及び弟妹 出生の日(養子縁組のときは、養子縁組の届出がされた日)
(ウ) 父母及び祖父母 満60歳の出生日に応当する日(満60歳以上で養子縁組したときは、養子縁組の届出がされた日)
(エ) 重度心身障害者 重度心身障害となった日
(オ) 退職 退職した日(退職日まで給与が支給されたときは、その日の翌日)
(カ) 事業等の廃業 事業等を廃業した日
(キ) 所得等の減少 年額90万円以上の所得が見込まれなくなった日(第1の2の(2)に掲げる所得の場合は、事業の縮小、資産の譲渡、災害等によるときはその事実のあった日、それら以外のときは翌年度の4月1日)
ウ 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において、「事実の生じた日」とは、配偶者が死亡した日、離婚の届出がされた日、未届の配偶者との離縁が証明された日等をいうものであること。
(2) 支給の停止又は支給額の減額
ア 職員が離職し、又は死亡した場合は、その離職し、又は死亡した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
イ 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において、「事実の生じた日」とは、次のそれぞれに掲げる日をいうものであること。ただし、それらの日前に職員が主として扶養しないこととなったときは、主として扶養しないこととなった日をいうものであること。
(ア) 満18歳に達した子、孫及び弟妹 満18歳の出生日に応当する日
(イ) 死亡 死亡した日
(ウ) 離婚(縁) 離婚(縁)の届出がされた日(未届の配偶者にあっては離縁が証明された日)
(エ) 就職 就職した日
(オ) 事業等の開業 事業等を開業した日
(カ) 年金、恩給、配当等 決定通知された日
(キ) 所得の増加 年額90万円以上の所得が見込まれることとなった日(第1の2の(2)に掲げる所得の場合は、事業の拡大、資産の取得等によるときはその事実のあった日、それら以外のときは翌年度の4月1日)
ウ 職員が児童手当法の規定により児童手当の支給を受ける場合は、その支給の対象となった月
エ 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
この場合において、「事実の生じた日」とは、婚姻の届出がされた日又は婚姻関係証明書により婚姻関係が証明された日をいうものであること。
(注)届出の期間15日の起算日は、事実の生じた日の翌日とする。ただし、満60歳の場合及び退職の場合は、事実の生じた日を起算日とする。
3 支給方法
(1) 扶養手当は、給料の支給方法に準じて月額で支給するものであること。なお、職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当の支給は、その月の給料の支給日に職員が所属する任命権者において支給するものであること。(
給与条例第15条第4項参照)
ア 停職にされている職員
イ 休職(無給の場合に限る。)にされている職員
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「組合専従許可」という。)を受けている職員
エ 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の許可(以下「育児休業許可」という。)を受けている職員
ア 職員が停職処分を受け、休職(給料等が全額支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、組合専従許可を受け、若しくは育児休業許可を受けた場合又はこれらの期間の終了により職務に復帰した場合(その月の初日から引き続いて停職、休職、組合専従又は育児休業の職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合においては、その月の扶養手当をその際に支給するものであること。)
イ 職員が非常の場合の費用に充てるため請求した場合(請求の日までの扶養手当をその際に支給するものであること。)
A 減給処分された場合
B 任命権者の承認なくして勤務しなかったため給料を減額された場合
第5 扶養親族台帳の管理
総務課長は、職員について扶養親族台帳(様式第6)を作成保管し、扶養親族の増員又は減員の認定を行ったときは、そのつど整理すること。
別紙 届出等書類
様式第1 扶養親族届
様式第2 婚姻関係証明書
様式第3 世帯員構成及び所得証明書
様式第4 雇用保険受給に関する証明書
様式第5 扶養状況申立書
様式第6 扶養親族台帳
様式第7 扶養親族現況届
様式第1~第7(省略)
 」と朱書し、第4により月額及び支給の開始年月を決定すること。(給与条例第13条第2項及び給与規則第3条第2項参照)
」と朱書し、第4により月額及び支給の開始年月を決定すること。(給与条例第13条第2項及び給与規則第3条第2項参照)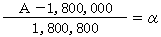 (小数点以下は、α<1のときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)、
(小数点以下は、α<1のときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)、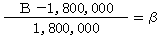 とする。
とする。